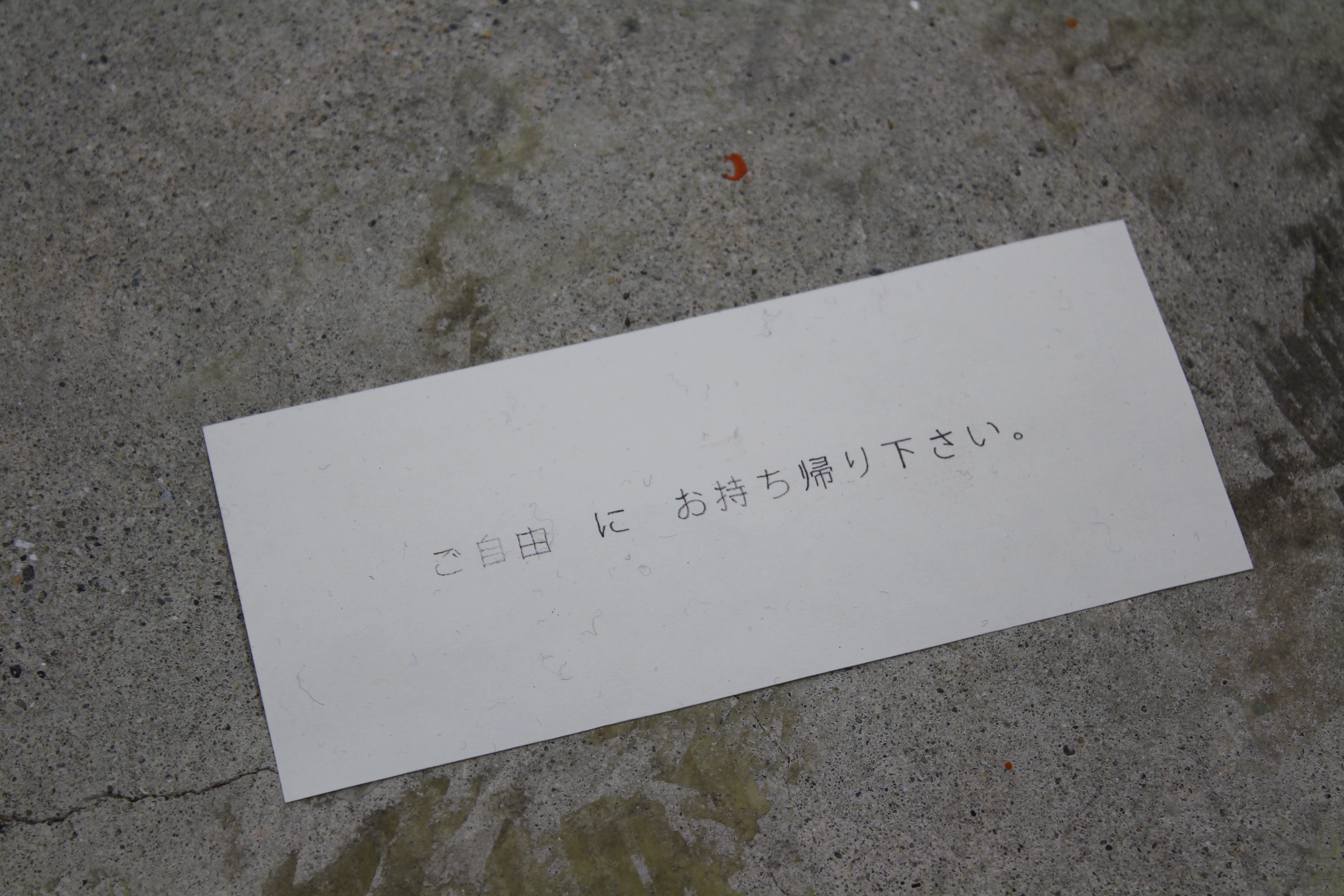2015年2月28日(土)- 3月7日(土)(会期中無休)
開廊時間:奥村直樹が起床してから就寝するまで
DESK/okumura ⧉(東京都中央区東日本橋3-1-8 2F)
【日本橋にある2つの場所】
日本橋・馬喰町のギャラリーAlainistheonlyoneにおいて佐々瞬の個展「とある日のこと(箱を受け取る)」が2月21日まで開催されていた。それは、一見すると、大小さまざまな段ボール箱が封をされて置かれているだけの展示だった。奥の壁に設えられた棚には、2段に分かれて8枚のテキストが置かれており、それらには、相異なる、箱をめぐる短い戯曲が記されている。その内容はいずれも、その場にある箱を1つ持ち帰る結末であり、実際、会場にも「ご自由 に お持ち帰り下さい。」(文字間のスペースはママ)というキャプションが認められた。この展覧会では鑑賞者が「作品」の一部を持ち帰ることができたのである。
ところで、芳名帳やプレスリリース、作家のポートフォリオが設置されているギャラリーの奥部には、高い棚が設けられ、こちらには封のされていない箱が7つ並べられていた。フタは開いているが、高い位置にあるために、やはり中身を見ることはできない。これらは《とある日のこと、その行方》と題された販売用の作品である。価格は39,000円、42,000円、46,000円が2つ、51,000円、53,000円、55,000円とバラつきがあり、それらには異なる素材で作られた「模型」が入っているという。箱の中身、すなわち「その行方」は作品のコレクターにしか知りえない――いかにも購買意欲をかき立てる仕掛けであるが、これだけでなく、個展の表題作である《とある日のこと》自体、同様の展示形態に3つのエディションが付され、それぞれ40万円で販売されているのである。今回の個展が第1版にあたり、残りの2つを購入することができる。
さて、展覧会を訪問したとき、私は箱のいくつかを振ってみて、中に何かが入っているのか確かめようとした。すると、軽いものが揺れてカタカタという音がする――その様子を、ギャラリーの奥からスタッフが訝しそうに見つめている。手に取りやすいサイズの箱は帯封が施されているが、一際大きな箱は――私が訪れたときには2つあった――フタがぐるりと一周、目張りされていた。私は最も小さな箱の1つを選んで、それを持ち帰った――。
持ち帰った箱を自宅で開封すると、その中に入っていたものは、空のプラスチックケースと、会場に設置されていたものと同様のテキストが1枚――フタの裏に綴じられていた。紛れもない「スカ」である。また「台本」を読み、再び佐々瞬の個展を訪れる――と言うのも、「今回の作品は、いくつかのテキストから始まります」と、佐々瞬自身がプレスリリースにおいて指示したとおり、これらの「台本」は展覧会の導入だったのである。まさしく「無限ループ」である。
私は自身の行いを恥じた――。会場の箱のうち、どれか1つを持ち帰ろうと決心したとき、最も小さいものを選んだ。しかし、どれでも良かったのである。選んではならなかったのである。本当に必要なことは、1つを選んで持ち帰り、自宅で中身を確認し、悦に入ることではなかった。この「作品」の「真実」に至るためには、ギャラリーに日参し、すべての箱の中身を確認しなければならなかったのである。仮に、来る日も来る日もギャラリーから小箱を持ち帰ることを繰り返すと考えたとき、私たちがたどりつくものとは何だろうか。その答えは明らかである――つまり、最後まで残されるだろう、大きな箱である。あのフタの目張りされた大きな箱こそが、発見されるべき「宝箱」だったに違いない。
それを実行することは、無論、困難である。しかし、ある男には容易いことであった。なぜなら、彼の自宅は、馬喰町駅を挟んでちょうどAlainistheonlyoneと反対の位置にあり、徒歩で10分とかからない場所だからである。その者こそ、奥村直樹である。奥村直樹は、平成元年生まれの若いアーティストである。布に描いた人物画《あれ奥村か》、および、それを路上の物品と交換する一連のパフォーマンス《あれ、奥村に見えるか》(3331アンデパンダン2013 スカラシップ受賞作)や、顔面だけを切り取ったぬいぐるみのアッサンブラージュ作品《ともだちたち》、期間限定のアート作品販売店《キラキラアートショップ》(yellowhouse)など、同一性や価値の不確かさ、代替可能性を問うような制作を行う。また、日本橋・横山町で、自宅の2階部分を改装したアーティスト・ラン・スペース「DESK/okumura」を営んでいる。ちなみに、奥村雄樹とは、とくに血縁関係はない。
会期最終日である21日――。私は奥村直樹と共に、再び佐々瞬の個展を訪れた。奥村は、その日の朝に自ら製作した台車を引き、Alainistheonlyoneにやってきた。大きな箱を2つ――最終日に残されていた大きな箱は、やはり2つだった――運び出し、それを台車に乗せて持ち帰った。ほどなくして会場に戻ってきた奥村は、続けて、残った小さな箱もすべて積み込もうとした。しかし、そこでギャラーのスタッフから制止を受けたのである。「常識的におかしい」という彼女の言葉は、たしかに、1人の手によって箱のすべてが持ち出されてしまうことの暴力性を非難したが、私たちにはそれをすることが許されていたはずである。つまり、鑑賞者は1人1つの箱を持ち帰ることが期待されているとはいえ、複数の箱を持ち出すこと、あるいは、それをくり返すことによって、すべての箱を一挙に手に入れることは、論理的に可能である。用意されたすべての箱が持ち帰られ、会場が「がらんどう」である状態も、佐々瞬の個展が見せ得る1つの姿だったはずである。
しかし、ついに奥村はすべての箱を持ち出すことに成功しなかった。なぜならば、大量の箱を持ち帰ろうとする来場者を制止することは、あらかじめ佐々瞬によって指示されている、と言うからである。そもそも、この展覧会には、いくつかの隠されたルールのあることが示唆されていた。やはりプレスリリースにおける記述によれば、「とある日のこと(箱を受け取る)」という作品タイトルの意味について、はじめは「もし理解できないならギャラリーに聞いてみることをおすすめします」としながらも、すぐに「実は「作品タイトルの意味をギャラリーに聞け」というのはウソで、聞いても教えてくれません。/何故なら僕が口止めしているからです。/それ以外にも、いくつかのことについて口止めしてあります」と翻している。
奥村の試みによって、図らずも、その一部を垣間見ることができたが、重要なことは、佐々瞬作品における「設定」を明らかにすることではない。私たちは「1人2つまでなら」というディレクターの言葉に従って――その場に居合わせた来場者の数4人にかけて――8つの箱を奥村の自宅へ持ち帰ることができた。ただし、奥村の当初の試みが奏功したとしても、それは不完全なものである定めだったことは言うまでもない。会期を通して、すでに何人かの鑑賞者によって箱のいくつかは奪われており、すべての箱の中身を確認することは叶わないからである。
さしあたり、私たちは、大小合わせて10個の段ボール箱を開封した。その中身は、内側がアルミ張りされた木製の重たい箱、菓子の箱、シューズの箱、筒、缶など――いずれも、やはり空箱だった。一方、フタに添付されていたテキストを確認すると、すべて【空箱のある空間】という但し書きで始まる、同一のものだった――。
私は二重に間違っていたのである。それは、会場に設置されていたテキスト――列挙すれば、【とあるギャラリー】【美術館の備品庫】【広い空間】【何もない空間】【何もない舞台】【いくつかの箱がある空間】【いくつもの箱がある空間】【箱が並ぶ空間。箱を手に取るシーン】の8種類――とは異なる、第9の「台本」だったのである。そこに記されていたものとは、けっして――再び――ギャラリーから箱を持ち出すことではなく、単に「受取ったその箱を、大事にしてください」という願いだけだった。
そして、箱のなかの空箱は「スカ」ではなかった――。むしろ、「箱を受け取る」と言うときの「箱」とは、これらの空箱に他ならなかったのである。作品タイトルの意味についてギャラリーに訊ねること――それは「箱の中身は何か」と質問することと同義だったのである。つまり、佐々瞬は――それこそ来場者が禁じられていた――「せっかちな好奇心」を抑圧し、箱を持ち帰り、それぞれの手で――あるいは眼で――中身を確かめるという鑑賞を促していたのである。このとき、箱の中身が何であるかということ自体には意味がない。私たちが持ち帰ったものは「作品」の一部などではなく、私たちが箱を持ち帰ること自体が佐々瞬の「作品」なのである。実際に佐々瞬の個展に訪れ、箱を持ち帰った諸氏においては言わずもがなの真実を、いまここで、いくら強調してもし過ぎることはない。
奥村直樹は、個展《佐々瞬「とある日のこと(箱を開ける)」》を開催する。台車を製作し、Alainistheonlyoneから多数の箱を持ち去り、それらを勝手に展示するというパフォーマンスは、佐々瞬によってすべて想定されていた――すくなくとも、想定されていたと考えるべき――範囲内であり、佐々瞬作品に対する鑑賞というふるまいの範疇を逸脱し得ない。よって、本人の与り知らぬところで展覧会が開かれることも、《とある日のこと》という作品の一部であると言わなければならない。結局、私たちは、佐々瞬の「掌の上」で踊らされているに過ぎないのである。
つまり、たとえ本人の許可や認知がなくとも、これは佐々瞬の個展に他ならない。そして、これを佐々瞬は中止させてはならない。なぜならば――たとえば、怒りによって拒否する場合、これが佐々瞬の作品ではないことを自ら認めてしまうからである。あるいは、40万円の価格を付けた《とある日のこと》を無断で展示したとして代金を請求する場合、やはり、自身の作品を放棄するばかりか――それは、作品を単なる「物」としてしか捉えない姿勢に他ならず――「出来事」として見出した自らの作品の特質性までをも否定してしまうからである。もし、佐々瞬が「掌」を返したなら、奥村のパフォーマンスは佐々瞬作品の内部から解放される――むしろ、かえって佐々瞬作品が奥村のパフォーマンスのもとに位置付け直されるだろう。そのときこそ、佐々瞬に対する批評が可能になるかもしれない――あるいは、一連の奥村の仕事こそが、佐々瞬に対する批評なのである。
2015年2月